2025年第4回定例道議会に向けた民主・道民連合政策審議会との政策協議及び北海道結志会との意見交換を実施
【連合北海道・政策情報No.1(2025年11月10日)】
2025年11月5日(水)、連合北海道は民主・道民連合政策審議会との政策協議及び北海道結志会との意見交換を実施した。民主・道民連合からは、畠山みのり政審会長、鈴木一磨政審筆頭副会長、田中勝一議員、渕上綾子議員、山根まさひろ議員、清水敬弘議員、宮崎アカネ議員、鈴木仁志議員、小泉真志議員、小林千代美議員、川澄宗之介議員、岡田遼議員の12名が参加した。
冒頭、畠山みのり民主・道民連合議員会政策審議会長は、「道議会の決算特別委員会が11月7日から11月13日まで予定されており、その後、第4回定例道議会が11月26日から12月12日までの会期予定となっている。タイトなスケジュールとなっているが、連合北海道との政策協議にあたってはこれまで以上に連携を深めてまいりたい」と挨拶した。
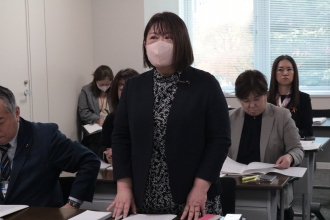
民主・道民連合政策審議会・畠山みのり政審会長の挨拶
次に連合北海道の永田政策・政治局長より、①第3回定例道議会以降の連合北海道の政策に関する経過報告をはじめ、②連合北海道第39回定期大会の開催及び役員体制、③2026春季生活闘争基本構想(案)、④2026年度政府予算に対する「要求と提言」中央省庁への要請行動(意見交換)、⑤2026年度道政に対する「要求と提言」対道交渉(意見交換)などの概要を説明した。
意見交換の場においては、山根まさひろ議員からは「北海道道議会の産炭地域振興・GX推進・エネルギー調査特別委員会と総務委員会の連合審査会は11月20日・21日の両日に参考人招致を行う予定となっている。参考人招致には、泊原子力発電所3号機の再稼働の必要性や安全対策に関する議論を深めていくこととなる」との情報提供があった。
鈴木一磨政審筆頭副会長からは「連合北海道の対道交渉の資料内容については、第4回定例道議会等のなかでも活かしていきたい。第4回定例道議会においては、第3期北海道創生総合戦略の見直しを含め、人口減対策や地方財政の確立、地域公共交通、地域医療などについて中央集権的な動きが加速しないよう地方から国へ訴えていかなければならないことから、知事が北海道ビジョンをどのように描いていくのかを追及していきたい」との意見があった。
同日開催した、北海道結志会との意見交換では、佐藤伸弥会長をはじめ、赤根広介幹事長、池本柳次議員、滝口信喜議員、新沼透議員、石川さわ子議員、水口典一議員、白川祥二議員の8名が参加した。
はじめに、永田政策・政治局長が民主・道民連合政策審議会と同様、資料に基づき説明後、意見交換を行った。滝口信喜議員からは「病床数に関する国の補助金は当初、民間病院を救済するための制度であった。北海道は圧倒的に公的病院が多いことから本州とは差がある。したがって、病床数がどのくらい必要かという議論になれば、道内の場合は市町村率が多いことから市町村で、ある程度の数字を出していかなければならない。地域医療構想では2次医療圏の必要病床数は決定できるが、個々の病院における病床数の増減数が決まらず問題となっている。総体的な病床減は算出できるものの、各病院に対応しなければ『1病床減らすごとに約410万円を医療機関に補助する』といった国の施策の試算にも計上することができない。必要病床数を一度削減すると復活できないことから余剰の病床数を抱えてきたという経過も踏まえて課題を整理する必要がある。また、地域医療について対道交渉をするときは保健福祉部地域医療課のみならず、自治体病院を管轄する市町村課も呼ぶべきではないか」と提起した。これに対し永田政策・政治局長は「必要病床数については、市町村任せではなく、鈴木北海道知事がリーダーシップを発揮して道庁自らがイニシアチブをとって地域医療の枠組みをどうすべきなのかを考えるべきである」と述べた。

北海道結志会との意見交換の様子
池本柳次議員からは「国は、原子力発電所の再稼働について入口の議論はあるものの出口の話が進まない。再稼働した場合、核のゴミは必ず出る。しかしそのゴミについては一切の安全基準を持たない。また、地域にお金を出して文献調査まで行ってきたがそこから先が進まない。これではエネルギーの国策として無責任ではないか。原子力発電のゴミは必ず出ることを踏まえ、ゴミの処理の方法や安全基準含めて国がきちんと示したうえで稼働の議論をするのであればまだしも、国は『特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律』(以下最終処分法という)を施行したものの、ゴミの最終処分の仕方は触れずじまいで、調査については地方に丸投げをして様子をみているのであれば、国はあまりにも無責任であるということを国会のなかでも議論してもらいたい」と述べた。また、以前NUMO(原子力発電環境整備機構)と議論した際、池本柳次議員が「深地層を最終処分地としてなぜ目を付けたのか」と質問を投げかけたことに対し、NUMOの伊藤理事は「日本は世界に誇る青函トンネルの技術がある。この技術に我々は目を付けた」と回答したとのエピソードも交えた。
石川さわ子道議は「最終処分法は安全に地層処分できるという前提で進んでいる法律で、突如として処分地をどこにするかという立て付けである。最終処分法の改正に向けた提案が難しいことは受け止めてはいるが、まずは議論のテーブルに載せることから行っていかなければならない」と問題提起した。
最後に永田政策・政治局長は、「連合北海道の原子力エネルギーに関する基本的考え方は『原子力発電は過渡的エネルギーであると位置づけ、脱原発、省エネ、新エネを推進する』とした2005年の組織財政特別委員会第6次答申(第18回定期大会確認)に基づいている。加えて、2012年に開催した連合北海道エネルギー・環境政策委員会『中間整理』では、『停止中の原子力発電所の運転再開を検討する条件は、福島第一原子力発電所の事故原因の検証結果を踏まえた、より高度な安全基準が設定され、それに基づく安全対策が実施されることを基本とすべき』などと取りまとめた経過がある。今後、原子力エネルギーに関する連合北海道の考え方をさらに整理していく必要がある」と述べ、意見交換を終了した。
以上


